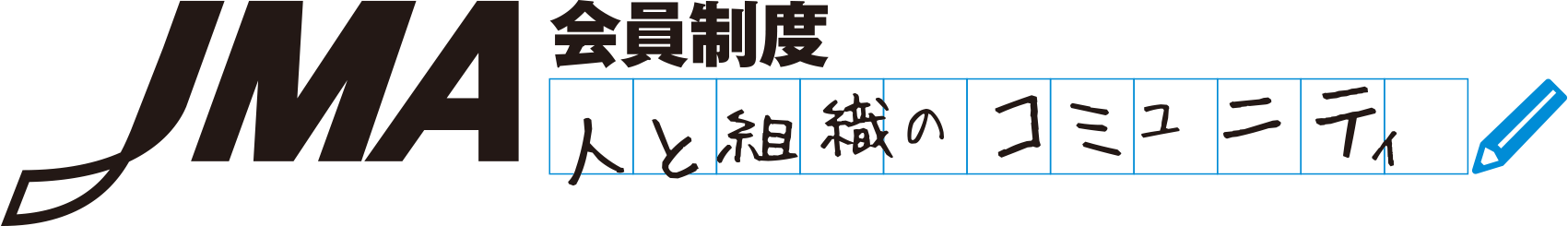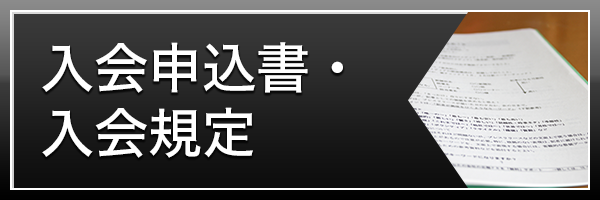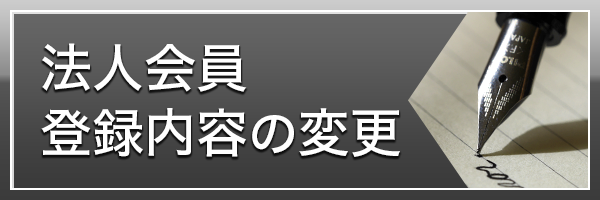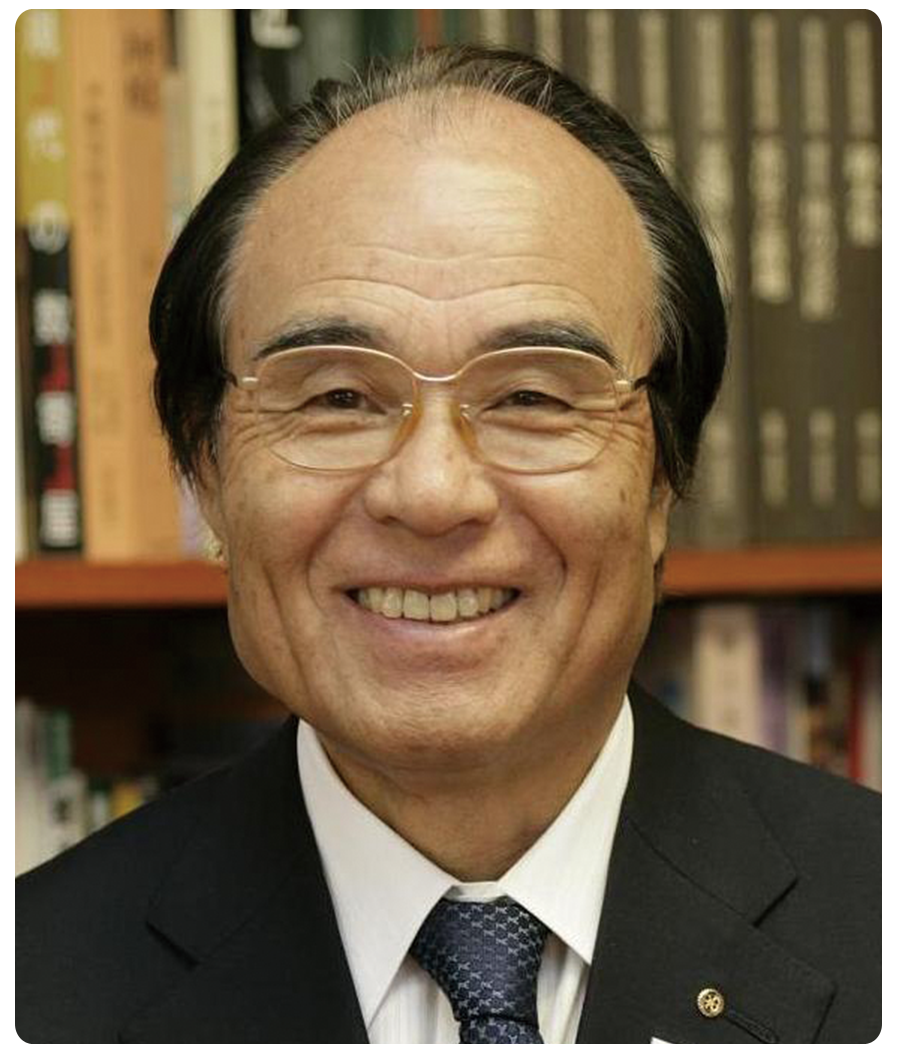開催レポート/一隅会第553回 時代を超えて輝く日本の伝統工芸の伝承と地域共創
~日本の美意識“用の美”が切り拓くグローバルな未来~2025年5月28日(水)
2025年5月28日(水)に第553回一隅会(経営哲学懇話会)をオンライン開催させていただきました。
今回の懇話会は、「時代を超えて輝く日本の伝統工芸の伝承と地域共創 ~日本の美意識”用の美”が切り拓くグローバルな未来~」をテーマに、日本工芸株式会社 代表取締役 松澤 斉之氏をお招きしました。
当日は、会員企業の132名にお申込みをいただき、講話の後には、質疑応答のお時間もあり、参加者との活発な意見交換がされました。
当日は4つの論点に的を絞り、日本の伝統工芸をご紹介くださいました。
日本の伝統工芸品の魅力は伝統行事、デザイン、歴史・起源、技術、自然・地理、美意識と様々な切り口で語られます。
今では海外での強い需要・人気で生産が追い付かない工芸品や著名人のSNS発信で入手困難になる品もあるとのことです。
日本の伝統工芸と現代に活きる「用の美」は素材の本質を活かし、無駄を省いたシンプルさ、機能性と美の調和、経年変化を愉しみ伝統技術の文脈を提示し、近年では「サステナブル」「丁寧な暮らし」「SDGs」にも繋がっています。
伝統工芸と地域活性化 ― 職人とのコラボレーション
伝統的工芸品の生産額は1983年をピークに2015年は1/5に減少していますが、「用の美」を世界に発信することにより、未来の可能性は大いに高まると考えられています。
現在では、伝統工芸と異分野の共創の兆しが見えており、異分野とのコラボ、オンラインの販路、現代に適応するデザイン・用途、伝統工芸体験、女性職人の増加傾向など新たな動きが各地で加速しています。
参加者との質疑応答、意見交換一部内容
Q:「用の美」と言いますが、実際は高額のため手が出ないので、今後どのように揃えばよろしいでしょうか。
A:高額設定の1つに工数、時間の背景があります。購入しやすい価格、使いやすいものを選び、作り手の思いを感じ取りながら使用するのが良いと思います。
Q:伝統工芸品の魅力に素材感、職人技による仕上がりの美しさ、実用時の心地よい手作り感などがありますが、いずれもeコマースの画面越しでは伝えづらいと思います。こうした魅力を伝えるにあたり画面上ではどのような工夫をされていますか。
A:商品の良さ、本来の見え方は商品ごとに違うので、できる限り目で見た近い状態での撮影場所を選び、どの角度から光を当てればきれいに見えるのか光の当て方を選び、日々工夫して磨いている状況です。
また、製造プロセス、工房に行った時のシーンや作り方を出来る限り他の媒体SNS等を活用し、複合的に理解を深めて継続していきたいと考えております。
Q:甲州印伝を愛用しており、印伝=甲州と思っておりましたが、貴社サイトで大和印伝を初めて知りました。どのようにしてご縁ができたのでしょうか。
A:基本的にほとんどのメーカーは紹介いただいております。
大和印伝に関しては、奈良に日本刀を作っている職人さんの息子さんが日本刀の販売を中心に行っており、お父様の工房に行った帰りに大和印伝の工房をご紹介いただいた次第です。
Q:海外にも様々な歴史や文化がありますが、その中で日本文化の魅力や独自性はどのような部分にあるとお考えでしょうか。海外の方が見た場合、どのような点が魅力的に映るとお考えでしょうか。
A:日本の独自性は産品によって異なり、長く続いているのが共通点であり魅力の一つであると考えております。長さは技術では獲得できないので、現代の生活にフィットしながらアレンジし、残すものは残し進化させているのが伝統工芸品の特徴として見受けられます。
Q:現代の「サステナブル」「丁寧なくらし」「SDGs」とも共鳴とテキストにも書いておりましたが、他に同様の事例はありますか。
A:備前焼は古くて歴史があり、進化し続けている象徴的な産地です。
職人の方は地元のどこに良い土があるかを熟知しており、自分たちの工房の横で調達した土を長年育て上げているので、正しくSDGsな取り組みです。
最後に松澤 斉之氏より、作り手と使われる方の間に入り、日本文化の本質、伝統工芸の理解を一層深め、日本に根付いている良いものを発信し、継承していきたいと述べられました。
今後は接点があれば企業とのコラボ、日本文化を国内外へ発信する取り組みも行いたいと展望をいただきました。

松澤 斉之 氏
日本工芸 株式会社 代表取締役
東京理科大学卒業。
ヤオハンジャパンでの倒産経験を契機に教育事業に転身し、起業家育成学校の事務局長を 歴任。
2012年からはアマゾンジャパンでシニアバイイングマネジャーとして従事。
2016年に日本工芸株式会社 を設立し、全国の伝統工芸産地を訪れ、生産者との密接な関係を築きながら工芸ギフトのオンライン販売事業「日本工芸堂」を展開。
日本経済新聞やWall Street International Magazineなどにも取り上げられる。
伝統工芸を活用した事業開発プロジェクトでは、上場企業との連携実績も多数。
NEC、パナソニック、早稲田大学、信金中央金庫、東京都などでの講演実績がある。