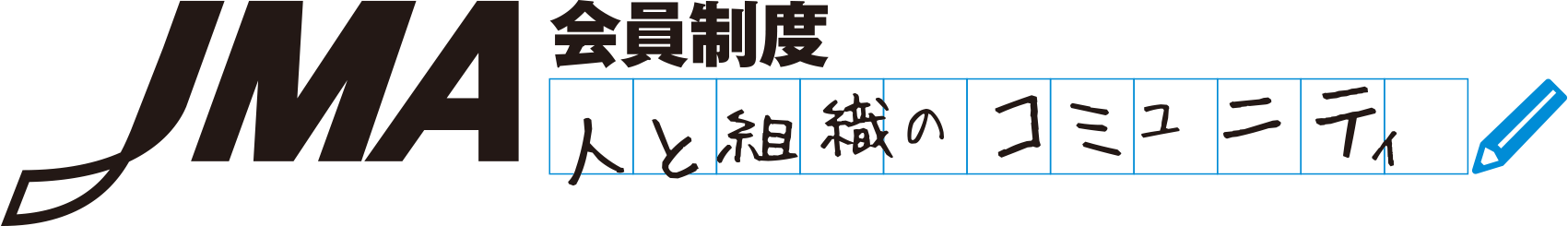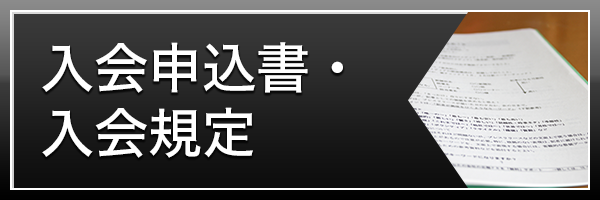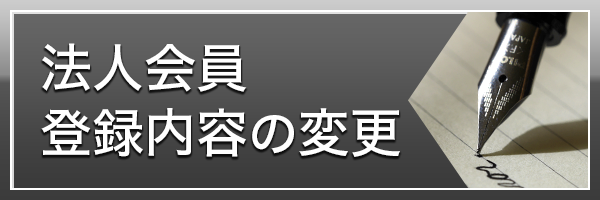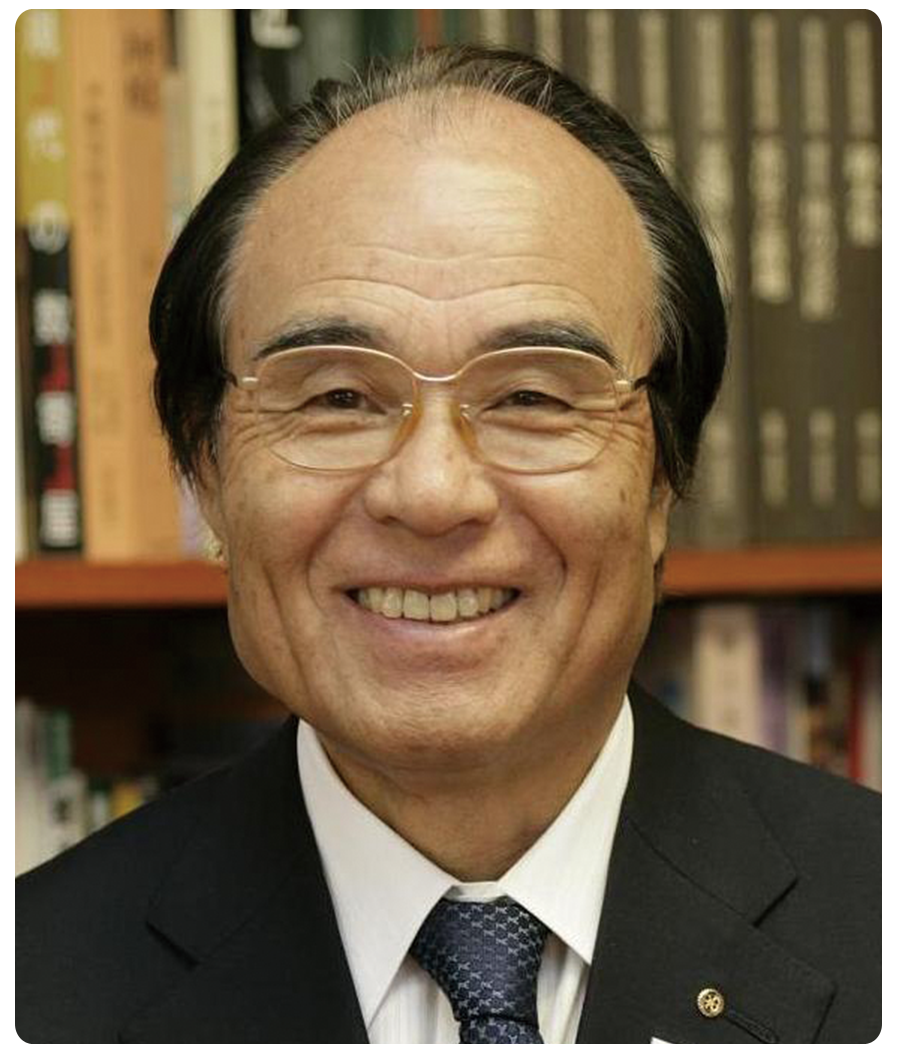開催レポート/JMAマネジメント講演会AI時代における「つながりと信頼」による自己ブランディング
〜個々の信頼の広がりが、組織全体の価値を高める〜2025年10月1日(水)
2025年10月1日(水)に第6回JMAマネジメント講演会をオンライン開催させていただきました。
今回の講演会は、AI時代における「つながりと信頼」による自己ブランディング~個々の信頼の広がりが、組織全体の価値を高める~をテーマに、株式会社アースメディア 代表取締役 松本 淳氏をお招きしました。
当日は会員企業141名にお申込みいただき、講話の後には質疑応答の時間を設け、参加者と活発な意見交換が行われました。
当日は9つの論点に的を絞り、「自己ブランディング」という言葉を誤解することなく、他者との「つながりと信頼」に重きをおいて、自分の存在を正しく社会に示し、活躍の場を増やすことを、分かり易く講説いただきました。
1. 社会/ビジネス環境の大きな変化
生成AIは浸透しているが、情報が拡散し過ぎて人間が書いても追いつかない時代に入り、「信頼」がより大事になった。
SNSも自動投稿が増えたが、AIの文章だと分かると、人間が書いておらずいい加減だと思い、一瞬にして読む気が失せる。
人間が書く事が最重要であり、あらかじめ「実際の存在を証明する」ことで価値が高まる。
2. なぜ自己ブランディングが必要なのか
匿名ではなく「自分」だから価値がある、人間が監修している。
自分が誰であるかを証明する必要がある。
情報発信前に自分の存在、信頼を構築し正しく認識されるよう、普段から発信して周りの方々と信頼関係を築くことが大事である。
ブランディングは飾ることではなく、ありのままの自分で、盛らず自分を出すことが大事。
「自己開示」しないと信頼されないし、リスクは全く感じられない。
自分の内面を磨き、素直に自己開示することがブランディングであり、それによって一層人格を磨き、円滑な人間関係を保つことが出来る。
自己開示をして共感を持ってもらうと、知名度が上がり信頼も得る。
3. この時代における自己ブランディングとは
「法人」ブランディングも大事ではあるが、今や主体がブランディングしやすい「個人」に移っており、従業員がどんな人でどんな想いでやっているのか、と言う意識に重要性が移ってきているので、個人が主役になりつつある。
SNSでは大組織の法人アカウントより、自己開示をする面白い一個人のアカウントが強く、信頼してもらえる。
4. ブランディングの本質
「有名であること」だけでは不十分、知っているかつ信頼できる、キーワードは共感できること。
ブランドは知名度ではなく、コアな方々にいかに信頼されているか、それがブランドの本質である。
能力や機能のみならず、「背景と文脈」が重要であり、口コミ、他者に語ってもらうことによって、信頼されブランドを支える。
ファン、結束、繋がり、お互いの人間関係の形成がSNSの世界に移ってきている。
5. どこからスタートするか
今やSNSの広がりが大きいので、まずは「自分の発信拠点」を確保する。
検索されたとき、「存在する」こと、自分の名前を置いておくこと。
自分の大事に思っている価値観を「棚卸し」して自己紹介をすると、「発信」の準備に非常に大きな効果がある。
6. ネットワークを拡大する
自分からネットワークを広げる努力が重要、つながってくださいとお願いされると嬉しいものである。
ネットワークが広がると、運用効果が飛躍的に増大、拡大には「複利」という考えを重視する。
リアクションはつながりが多いともらえ、結果自分の投稿が保証された状態が届く。
LinkedInが唯一実名文化でパブリック性がある。
7. まずは「他者に貢献」すること
発信前にコミュニケーションの意識、傾聴が大事、まずは読んでリアクションをすること。
相手にリアクションすると、関係性が強化され、結果自分の投稿が優遇され、拡散される。
8. 発信するということ
続かないのが一番難敵なので、とにかく続けること。
難しい話より自分の身近な話がよい。
宣伝する前にリレーションを作り、宣伝のバランスを考えよう。
有益かつ刺さる自己開示をすることにより、バズる。
Thought Leadership ― 自分の思想、発想を出していこう。
組織のなかでは全ての人がリーダーであり、自己を主張し、かつリーダーシップを持って引っ張っていくイメージ。これが大事であり、コアの自己ブランディングである。
9. 個々のブランディングが、組織全体の信頼と価値を高める
SNSを取り入れている企業は増えており、個人の尊厳、自由と責任、自分の意見を述べる多様性を確立している組織は強い。
組織内だけの知名度ではなく「社会における知名度」の向上、自分だけのメディア・プロフィール・ページで発信し、社会とダイレクトな繋がりを持ち、個人がボトムアップで組織のブランドを上げていく世界になっていく。
「自由に発信できる風土とルール」づくりが必要である。
組織で伸ばすためには「チーム戦」、横の繋がりが大事で、個人同士が互いを助け、「コメント」も重要なコンテンツである。
成功例だと、役員と新人がきちんとフラットに議論が交わされ、展開されている時があるが、非常に良いコンテンツで、そのような運用が理想である。
公式アカウントはお互いを応援して、さらに公式アカウントで発信したものを皆でシェアしたり支えたりして、はじめて公式アカウントが伸びる。個々が強くなってその結果公式アカウントが強くなるのが理想かと思う。
以下、Q&Aセッションの内容
Q:所属組織のブランディングの上で成り立っている個人のブランディングを、自己(個人の)ブランディングと混同されている方を見かける。組織のブランディングも活用し、個人としてのブランディングを構築するうえで、よくある課題とその対応策について、ご説明いただきたい。
A: 会社のブランド自慢は逆効果、会社の信頼を上手く使いながら個人のブランド促進は出来るし、個人の貢献が会社のブランドをアップし、お互いギブしあって、組織と個人が共同して高めあう関係性が理想であると思う。
Q:SNSをビジネスで利用する際、業務時間外での対応が増え、公私の境目がなくなりそうな気がするが、バランスの取り方など使い方のコツはあるか。
A: SNSの確認は、業務を圧迫したら意味がないので、休憩時間に息抜きを行って、長く時間を使わないようにしている。
但し、投稿に関しては投稿時間を1時間と決めて、書ききる訓練をしながら行っている。
経営者にお伝えしたいのは、SNSを投資と捉え、一定時間を利用して業務として行って欲しい。
Q:ネットでのコミュニケーション疲れを、効率よく進めるためのコツがあれば教えてほしい。
A: 投稿は自分でコントロール出来るが、コメントの交換及びDMは相手ありきなので大変になる可能性がある。これ以上質問は受けない、スタンプで一旦終わりなどルールを決めて、自分が返せるだけで十分だし、継続が大事なので無理せず自分でコントロールすることが大切だと思う。
Q:会社としてSNS規制を禁止している場合、それを打開する知恵、ヒントなどありましたら教えてほしい。
A: 役員、経営陣に理解してもらうしかない。何社か、若手がSNSの成功事例をプレゼンで訴えた例があるが、説得するしかない。SNS運用ルールを会社として整備すると、何を投稿してよいかなどを自分で判断しやすくなるため、ルールを作り機密事項を守り決めて、役員にも理解出来るよう訴えていくしかない。
Q:自社や個人のアカウントで、同業他社や競合企業をフォローしたり投稿に反応する場合、積極的にフォロー、リアクションする方が良いのでしょうか、それともあまり関わりを持たない企業の方が多いのか。
A: 会社が競合企業と関わるのを禁止していなければ、積極的に交流した方がいいと思う。
たとえば、大手コンサルティング会社のパートナーであるLinkedInインフルエンサーの投稿に対し、他の様々なファームのコンサルタントからもコメントが入り、会社を超えた交流が広がるという現象が起きている。このように業界全体で盛り上がるのが、理想のあり方だと考える。
Q:LinkedInはオフィシャル性の高い性質であるため、プライベートの投稿が難しいと思っている。参考になる投稿を教えてほしい。
A: 昨年の米国Bloombergの「LinkedInがFacebook化している」という記事で、欧米でも割とプライベートの投稿が増えている。変な自慢や内輪話でなければ、自分の趣味とかを伝えて良いと思う。
自分の趣味の話を皆さんにシェアして喜ばれるよう、捻って投稿するのがお薦めであり、
自分が普段思っていることを情報提供し、提示して投稿していくとコツも見つかるし良いと思う。
Q:企業ブランディング、商品・サービスブランディングを高める方法としても適応できるか。
A: SNSの場合、そのサービスの裏側に誰が居るのか、開発秘話や担当者のストーリーを出す方が評価は高いので、携わった人々の話を一緒に伝え、このサービスは素晴らしいと思うので使ってくださいとアプローチを行うと、SNSを中心にサービスの知名度が上がる。採用も同じで、SNSは自分の言葉で書くので、個々のメンバーが自社の良さを投稿するのが一番リアルで効果があるので、自主的に発信したくなるような土壌を作ると非常に効果が上がる。
Q:SNSを利用した採用が増えているにも関わらず、経営層は相変わらず理解不足です。何とか理解が高まるヒントはないか。
A: 内定者は、会社の内情を知りたいので、SNS上の退職者コメントより在籍社員コメントから読み取り、関係者のリアルな投稿が多い企業を選択する傾向がある。このような事例を伝えるとSNSの有効性を理解するかもしれない。
Q:Thought Leadershipについて興味深いので、もう少し詳しく教えてほしい。
A: 誰もがリーダーであり、人間が自分で責任を持ち、自分の核を持って変革したいと発信し、そこにメンバーが集まる。先ずは発信し、発信するとフォロワーシップの力が働くので、それが出来る土壌、カルチャーを作らないといけない。
Q:補足資料にも興味があるので、ご説明ください。
A: SNSの選び方、YouTube、TikTokはしっかりと発信すれば効果は大きい、ただコメントが匿名なので炎上もあるし、発信コストも高い。個人では限界があるので、テキストなら文章のみで、投資対効果を良くするために、テキストを中心に組んだ方がいいと思う。アメリカでは労働人口よりユーザーが多く、名刺がLinkedIn状態。日本は400万人と遅れをとりガラパコス状態であるため、少ない日本人ユーザーに注目が集まり、海外とも繋がるチャンスである。
最後に松本 淳氏より

松本 淳 氏
株式会社アースメディア 代表取締役
まずは自分の発信拠点を作り、最新の自己紹介を作成する。それだけでもチャンスは増え、さらにネットワークを広げて発信をする。予想以上の効果を実感でき、沢山の方と知り合えるので、自己ブランディング、発信を行っていきましょう。