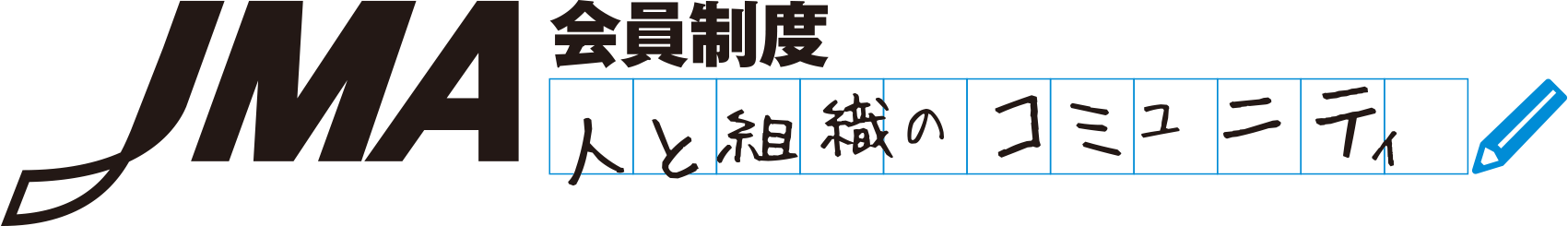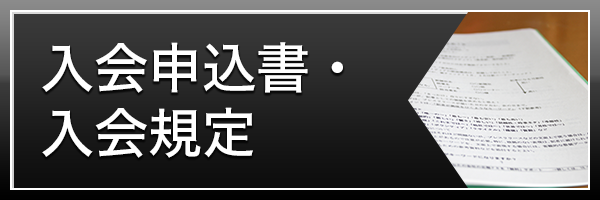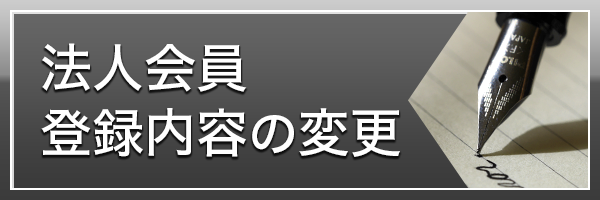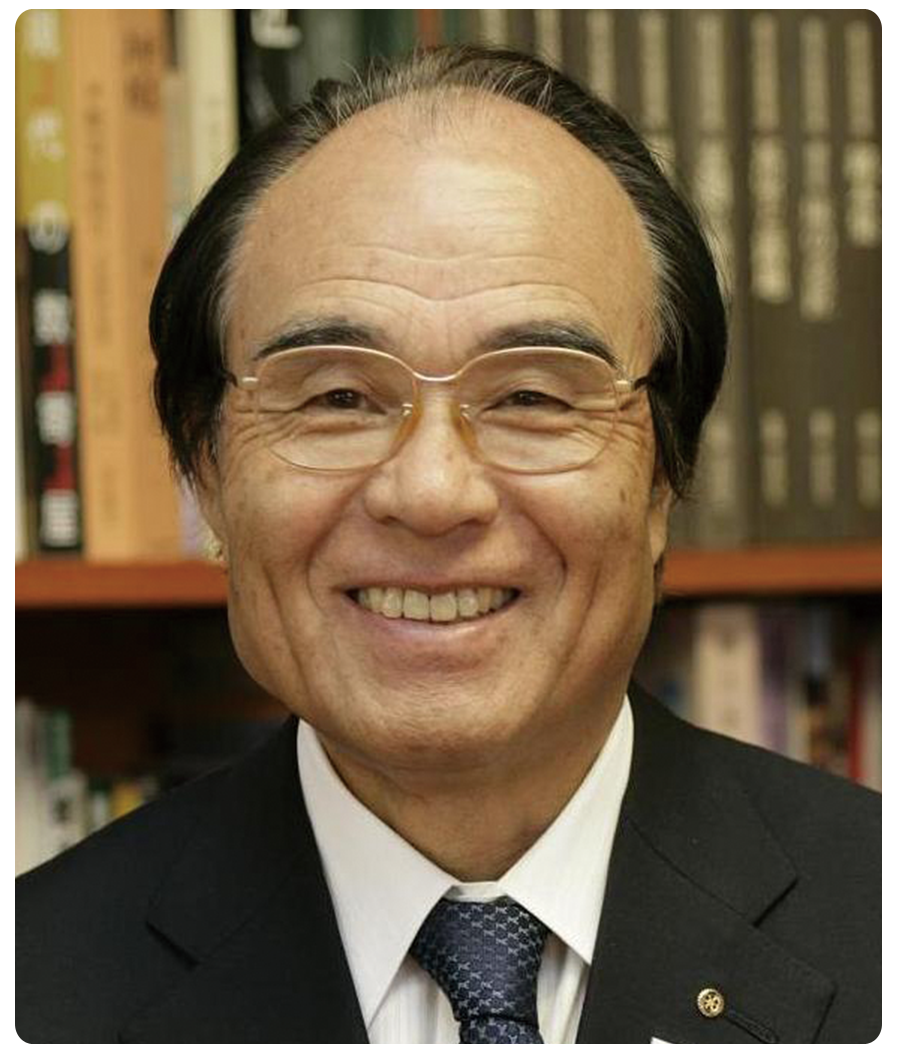開催レポート/JMAマネジメント講演会再点検!!従業員、工場・事業所を火災から守る危機管理
~職場でできる“命を守るため”の行動、日常準備~2025年9月3日(水)
2025年9月3日(水)に第5回JMAマネジメント講演会をオンライン開催いたしました。
今回の講演会は、「再点検!!従業員、工場・事業所を火災から守る危機管理 ~職場でできる“命を守るため”の行動、日常準備~」をテーマに、危機管理防災アドバイザー / 田中行政書士事務所 代表 / 株式会社アームレスキュー 代表取締役 田中 章 氏をお招きしました。
当日は会員企業163名にお申込みをいただき、講話の後には質疑応答の時間を設け、参加者と活発な意見交換が行われました。
当日は5つの論点に的を絞り、災害時・非常時には、経営者はじめ管理者・マネジメント層がリーダーとしてどう振る舞うべきか、また日常から従業員の自発性とモチベーションを高めつつ危機意識を醸成するかなど、実効性が高く、簡単にできる具体策を分かり易く講説いただきました。
1. 災害から従業員を守る:火災・風水害・地震への備え
火災
火災件数の約6割が一般住宅で、原因別ではたばこが一番多く、そのうち逃げ遅れによる死者の数が圧倒的に多い。
工場火災の約8割は工場作業場から出火、倉庫火災の約6割は倉庫内部からの出火である。
一般住宅が燃え尽きるまでにかかる時間はわずか20分。
風水害
「線状降水帯」による集中豪雨から身を守るには
- 日頃から、ハザードマップ(火災予測地域)で自宅、勤務先地域の危険性を認識しておくこと!!
- 大雨予報が出た段階で早めの避難を検討すること
- 大雨で避難が出来ない場合は垂直避難すること
- 山に近い場合は、山の斜面から離れ水平避難すること
地震
地震発生直後はまず身の安全を確保し、揺れがおさまったら出火防止を行い、近隣の安全確認を行うよう推奨している。
新たにラジオやテレビで正しい情報を得る。
土砂災害については兆候(少し急斜面から濁った水や石が落ちてくる、異臭が漂う)が見られるので、五感を使って確認すること。
非常時持出品は食料等の備蓄(3日分)の準備が必要。
ローリングストック法を推奨 → 普段食べるものを備え、食べたらまた買い足す
2. 災害リスクの理解と従業員の安全を最優先する意識
防災は意識して経験することが大切
警戒レベルは5段階で示されており、レベル3は高齢者等避難、レベル4は全員が避難である。
レベル3を記憶に留め、いのちを守る行動を取ってほしい。
3. 事例から見るオフィス・工場での迅速・的確な実践的対応
- 風水害は事前に予見できるので、事前準備と心構えが重要である。
- 防災訓練等の参加、訓練することにより体得する、頭では行動できない。
- 職場・家族・地域で話し合って、防災の意識を高めること。
4. 管理者として自発的な危機への備えをチームに浸透させる
平常時からリーダーとして地域住民・事業所で中心となり活動することで、災害時に先頭に立って、防災活動を主導していくことが出来る。
5. 命を守る日常の防災革命:安全・安心の職場づくり -訓練に終わりなし-
- 日常からの備えが命を守る
- 従業員の自発性と協力が鍵
- 継続的な教育と改善が重要
参加者との質疑応答の主な内容
Q:対応マニュアルの作成について、ポイントなどを解説してもらいたい。
A: 対応マニュアルは「誰が・いつ・何を・どうするか」が明確であることが重要で、以下のポイントを押さえて作成すると良い。
- 平時と災害時の役割分担の明確化: 部署ごと・職位ごとに行動を定義
- 初動対応の手順: 安否確認、避難誘導、通報など、最初の行動を具体的に
- 情報伝達ルートの整備: 連絡網やツール(LINE、社内システムなど)の活用
- 定期的な見直しと訓練: 年1回以上の訓練と、マニュアルの更新を推奨
- 図やチェックリストの活用: 視覚的に理解しやすく、現場で使いやすい形に
- 「読むマニュアル」ではなく、「使えるマニュアル」を目指すことが肝心
Q:危険の怖さ、危機の備えを部門内やチーム内に浸透させる秘訣やヒントを教えてほしい。
A: 他社から事故事例を収集し、色んなカードを持って、自分の引き出しを増やしていくのが非常に大切であり、危機意識を高める1つの法則になる。
Q:避難訓練は定期的に開催するが、参加意欲が低く感じるので、どうすれば自分事として捉えられるのか。
A: 避難訓練が毎年毎回、同じ想定のあらすじであると、危機管理意識は低下するので、このシナリオを変えていくのが1つの方策、或いはシナリオを部署毎に作り、全員参加型にしていくと危機意識は高まっていくかと思う。
Q:避難訓練がマンネリ化しており、対策として避難時の避難場所は複数あった方が良いのでしょうか。
A: 避難経路、避難場所は変えると混乱が生じるので、災害の想定をその都度変えていくのが良いかと思う。
Q:工場や事務所では安全第一で危機管理意識が高いと思いますが、管理部門が一番遅れていると思うが、いかがでしょうか。
A: 現場が一番、危機意識が高くなるが、研修制度や外部講師を取り入れ、様々なカテゴリーの中で災害対策を行うことによって新たな風が入ってくるので、現場サイド、管理部門の危機意識を高めるための工夫を行ってほしい。
Q:想定をどこまで考慮すべきか、津波・水害などハザードマップで示されるものの、費用対効果を考慮し、最低限の対策になりがちで、想定外は起こりえるため、どこまで対策を講じるべきか考え方のヒントを教えてほしい。
A: 費用対効果を考えるなら、現在の住まい、事業所をハザードマップで確認し、安全であるなら地震と火災対応、サイバーテロ、感染症を広く浅くカバーいただきたい。
Q:労災防止のKPI(重要業績評価指標)についてヒヤリハット以外の項目で具体的な例はあるか。
A: KYT(危険予知訓練) のカウント数を上げてほしい。また社外にも目を向け、何をどのように取り入れているのか、過去の災害事例を見ながら取り組んでいただきたい。
Q:ヒヤリハットが集まりにくくなってきており、効果的な活動はありますでしょうか。
A: ヒヤリハット件数が減少すると、安全対策を考えるデータが少なくなるので、些細なこと、このまま置いていたら事故になるのでは等、定期的に職員の方に挙げていっていただきたい。
Q:介護・福祉施設など高齢者や身障者がいる場合の危機管理準備、対策で大切なことがあればご教示ください。
A: 昨年、介護施設はBCP(事業継続計画)が義務化になった。入所されている方の命を守るために何をすれば良いのか、施設側で何が出来るのか、同業他社からの応援などが重要なポイントになるので、入居者、従業員の人数、その辺も含め準備・計画を行っていただきたい。
最後に田中 章 氏より

田中 章 氏
危機管理防災アドバイザー
田中行政書士事務所 代表
株式会社アームレスキュー 代表取締役
事業所の安心・安全を守るためのキーマンは「従業員」である。従業員の安否確認を含め、命を守るためにはどうしたらよいのか、ここを国も重要視している。
BCP(事業継続計画)を構築するとともに、従業員・その家族の命の安全を守るための計画を考えていってほしいと、メッセージをいただいた。