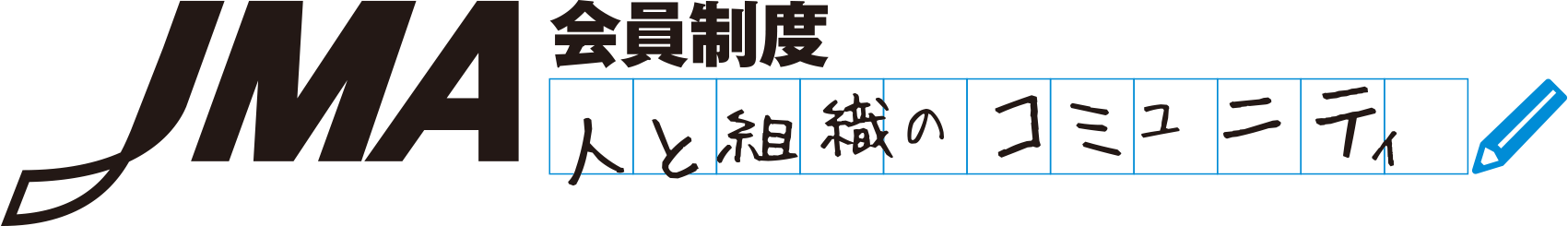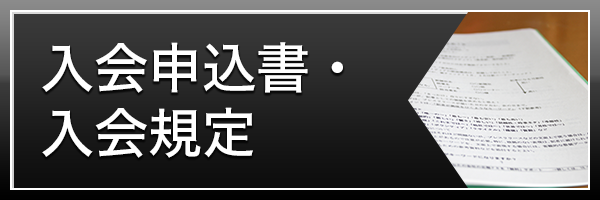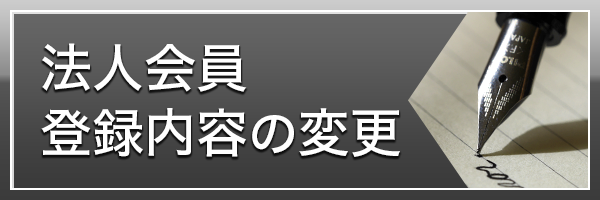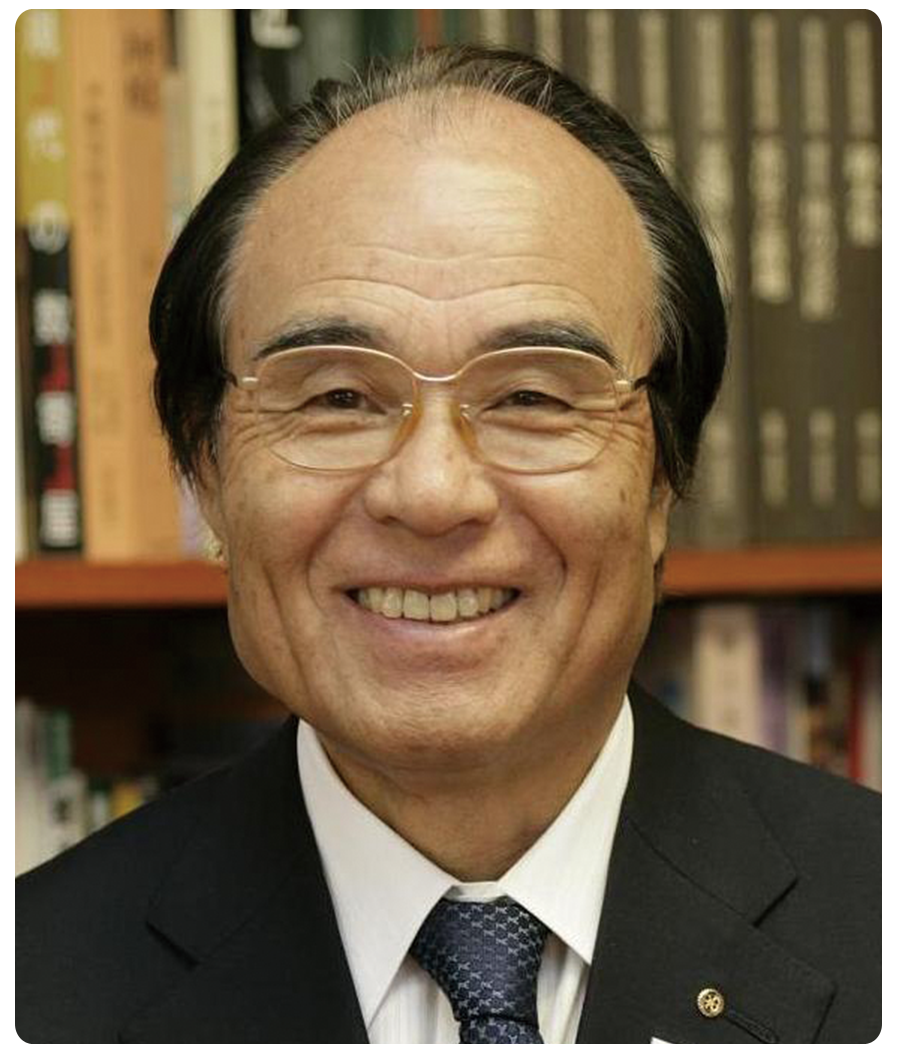開催レポート/JMAマネジメント講演会上手な「休養」の実践による企業力・組織力の飛躍的向上
〜日本人の8割が「疲れている」状態から脱却する休養マネジメント術〜2025年7月30日(水)
2025年7月30日(水)に第4回JMAマネジメント講演会をオンライン開催いたしました。
今回の講演会は、「上手な「休養」の実践による企業力・組織力の飛躍的向上 〜日本人の8割が「疲れている」状態から脱却する休養マネジメント術〜」をテーマに、一般社団法人日本リカバリー協会 代表理事/株式会社ベネクス 執行役員 片野 秀樹氏をお招きしました。
当日は会員企業231名にお申込みをいただき、講話の後には質疑応答の時間を設け、参加者と活発な意見交換が行われました。
1.3大生体アラーム(未病サイン)
発熱 痛み 疲労
疲労(病気になる前の身体が発するシグナル・サイン・アラート)を見落としがちだが、そのまま仕事や作業を続けると、病気へのリスクが高まる。
疲労は発熱・痛みを併せて、病気のサインであることを意識してほしい。
2.フィットネス疲労理論
「体力」―「疲労」=最大パフォーマンス
疲労の定義とは、過度の肉体および精神的活動、または疾病によって生じた「独特の不快感」と「休養の願望」を伴う身体の活動能力の減退状態である。
3.疲労と疲労感の違い
「疲労」は活動能力が低下であり、その時の不快感が「疲労感」である。
「疲労」と「疲労感」は常に一緒に動いており、疲労感がある時は、活動能力が下がっているので、本来は活動能力が高まるまで待つという選択をしなければならない。
4.リカバリーサイクル(攻めの休養)
現代は24時間戦える時代になったので、活力をしっかり高めるために、自分自身で積極的に能動的に休養を取って、意識的に活力を上げなければならない。
活力を高めるための攻めの休養は3つの休養、そして7つのタイプに分けられる。
リカバリーの定義(攻めの休養)とは、心身の活動能力の減退した機能を回復し、休養をもって生理的・心理的資本である活力を蓄えて次に備えることである。
5.働くひとのために
- 休養の目的を明確にする
- 余白で充電量(活力)を意識する
- オフタイムから仕事の時間を決める
→24時間のタイムマネジメント
→1週間のタイムマネジメント
まとめ:疲労対策は欲求に従う時代から、自らの攻めの休養の時代へ
Q:休む=怠けている、と誤解されやすい日本社会で、自分が疲れていると表明しやすい社会になっているとは言えないか。
A:日本社会は調和主義であり、周りの目を気にする。休むことをネガティブに考えず、休まないとしっかり活動が出来ないと社会がいち早く察知すべきである。
また日本人の特徴として女性は特に責任感が強く、様々な負担が多いため、この風習を改善しなければならないと考えている。
Q:片野先生が推進しているオフファーストの考えは、どのような利点があるのか。
A:休日2日間を先行意識化することで、行動が変わり、翌週5日間のパフォーマンスが高まると捉えている。
Q:攻めの休養にシフトしたいと考えているが、会社側に理解してもらう良いヒントがあれば教えてほしい。
A:社会や時代が移り変わっているので、休むことに対し上層部とディスカッションを行ったりして、理解を 高めてもらう必要がある。
Q:ストレスへの向き合い方を教えてほしい。
A:ストレスは避けて通れないが、活動能力を高め意識的に行えば行動も結果も変わっていく。
Q:一定の会社には産業医が配置されているが、産業医は休養学についてリテラシーは高いのか。
A:休養学はまだまだ認知が低く、産業医に対してセミナーを行うこともある。
我々は健康の分野、健康生成論の考えは、どうしたら健康になるか、人々が健康を維持・増進するための要因に焦点を当て、その要因を強化することで健康状態を良好にしようとする考え方である。
健康生成論の考えを持った医師はごく少数である。
Q:昼夜2交代の工場勤務で、決められたシフト・時間の元で働いています。仕事内容の裁量も少なく、休憩時間も厳しく決められており、このような働き方で休養のアドバイスがあれば教えてほしい。
A:リズムをなるべく維持する意識を持ってもらいたい。昼の勤務は起床時にしっかりと光を浴び、夜の勤務は逆に日中に光を浴びないよう心掛け、体内時計を逆転させるよう意識的に行うこと。
休憩時間をいかに効率的に過ごすかを意識してほしい。昼休みに仮眠をとったり、途中休憩の時にしっかり余白を作り、活力を高める行動、体操や気分転換を行うと良い。
休憩時間中に携帯をずっと見ていると、頭を休める休養時間に頭が活動してしまうので、控えてもらい 余白を上手に、活力を高める行動を取ってもらいたい。
Q:チームメンバーの健康に配慮する上で、肉体的な疲れだけでなく、脳や目が疲れると言う声があるが、こういったメンバーに助言があれば教えてほしい。
A:脳をいかにデフォルトモードに戻すかが大切で、頭を使っているワーキングモードを時々デフォルトモードにし、一旦情報を整理するタイミングを時々取り入れて欲しい。
少し余白を作り、自分自身で外を見たり、ぼんやりしてデフォルトモードにする行動を取るなどが、次の仕事への効率が高まる行動だと思う。
最後に片野 秀樹氏より

片野 秀樹 氏
一般社団法人日本リカバリー協会 代表理事/ 株式会社ベネクス 執行役員
休むことをポジティブに捉え、休む目的は次の生産性を高めることを意識するという機会になればと願う。周りの方々に疲労と疲労感、マスキングなどを伝え、自分自身の休養に関しての意識、休み方の発想 の切り替えを行ってほしい。
私もさらに発信力を高め、休養の大切さを伝えていきたいと思う。